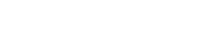こんにちは!広報部ふさピーです。
以前、こちらのBLOG&NEWSでの発信を増やしていきたいと宣言していたとおり、いたって地道にではありますが、着実に進めております。
バルトと私
さて、今回は、「メンバーのつぶやき」と簡単にご紹介していたシリーズの第一弾です。
このシリーズの趣旨は、「バルトでの仕事を通して実現したい社会/世界 ~バルトを通して見える世界(バルトと私)~ 」です
バルトのビジョン ー 老若男女のたゆみなき成長を通して社会を豊かにする ー
人が年齢性別関係なく、互いに切磋琢磨し、人として成長し続けることが、
社会の発展につながり、心が富み、豊かで持続可能なフィールドを形成していくこと
メンバー一人一人のフィルターを通してバルトのビジョンが表現できないかな、できるはずと思い、この企画を考えました。日々、どんなことを拠りどころとして仕事をしているのか、バルトのビジョンのもとに集った仲間たちがどんなことを感じているのかといったことを発信していけたらなと考えています。
「こんなことを考えている人たちがバルトにはいるんだね」と読んだ方のバルトへの理解が深まり、バルトのファンが増えたらいいなと願っています。
前置きはこれぐらいにして、記念すべきトップバッターはバルトの「仏」的存在、井澤さんです!
このシリーズが好評を博すかどうかは井澤さんにかかっています(w)
では、さっそく、バトンタッチいたしまーす!
ー 予実管理を通して社会の見方が変わる ー
はじめに
こんにちは、井澤です!
さて、いきなりですが“バルトの仕事を通して実現したい社会や、仕事を通して見える世界を発信していこう という企画が始まりました。
バルトの理念である 成長できるフィールド作り を実現するため、メンバー自身が“VALTの考え方と向き合い、VALTビジョンの解像度を深めること”に繋げていこうと思います。
また、弊社メンバーの想いを伝えることで、1人でも共感、賛同いただけるような方が増えれば何よりです。
予実管理とは?
私が考えたテーマは ”予実管理を通して社会の見方が変わる”です。
ただ一口に予実管理といってもピンと来ないかもしれません。
予実管理がどういうものかというと、制作などのプロジェクトを進行する際に、デザイン制作費用が50,000円、ウェブページ制作費用が50,000円というように工程ごとに予算を割り振り、予算内でプロジェクトを達成することを目標に予算と実績を管理していこう、というものです。
別の言い方をすれば、「感覚ではなく数字を元にプロジェクトを進める」ことがポイントだと思います。
なぜ予実管理を行っているかについて、会社経営が続けば続くほど紆余曲折あるもので、、、受注額以上のコストをかけてプロジェクトを完了させることが多々ありました
(受注額の倍以上のコストをかけたことも!)。
もうお分かりかと思いますが、会社経営が危機的状況に陥ったのはコストバランスの悪さが原因でした。
そうです、コストバランスの悪さをテコ入れするために予実管理を行っているのです。
もし予実管理に関心がある方は、弊社の WALZというサービスをご覧ください。
予実管理と向き合う

会社のミッションとして予実管理を行うことになったものの、私は数字が苦手で数字をみるのが嫌で嫌で仕方がない人間でした。
大きな声では言えませんが、高校時代に数学で2を取ったことがあります。
もちろん10段階評価の2です(笑)
いまだに数字に対して苦手意識は払拭されていませんが、数字を見る機会が増え、数字に慣れてきているからか少しずつ苦手意識が緩和されているような気がします。
ただし全てのプロジェクトで黒字を出すことは難しく、まだまだ赤字を出すことがありますが、予実管理を続けることで間違いなく赤字は減りました。そして、赤字体質の解消に繋がるものだと理解できてきました。
予実管理で変わった社会の見方

数字を見つめることで得た副産物として、世の中を数字で見ようという意識が出てきました。
例えば飲食店で食事をした際に、感覚的ではなく人件費や原価率を想像し経営努力を見出してみたり、
プライベートで何らかの見積を取ることがあれば数字の妥当性を調べてみたり、政党助成金の使途報告書を見たり、など数字で社会を見る目が養われたと思います。
予実管理をする前は、飲食店で時折新メニューや企画メニューが出る理由は、メニューを停滞させずリピーターを飽きさせない定性的な施策だと考えていました。
ただし予実管理を始めてからは、一定の原価率を超えないように素材の相場を鑑みつつ、原価が低く品質の高い素材を選定しコストと品質のバランスが取れたメニューを提供する飲食店があることを感じるようになりました。
これは定量的に新メニューや企画メニューの施策を行っているということだと思います。
考えてみれば当たり前のことなのかもしれませんが、当たり前のことを継続するのは非常に難しく、そのような経営努力をしているお店は応援したくなります(笑)
最後に
数字が苦手なのは相変わらずですが、予実管理を行うことで物の見方に幅ができたと思います。数字が苦手な方は沢山いると思いますが、身近で取り組みやすい予実管理は ”家計簿” ですね。
私は数字に慣れるために一時的に家計簿をつけていましたが、不要なサービスを解約し、余った費用で必要なサービスを契約するなど、プライベートでも予実管理の考え方が有意義に働きました。
数字が苦手な方は恐らく学生時代のイメージを引きずっている方が多いと思いますが、もう一度数字と触れ合ってみると新たな発見があるかもしれません。
本記事をご覧になって少しでも関心が出た方は数字に触れる機会をぜひ作ってみてください。