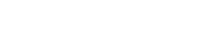〜Art Osaka 2025レポート〜
こんにちは。株式会社VALTでデザイナー兼広報をしているジョイです。
私たちVALTは 「文化」「観光」「ミュージアムDX」領域で事業を展開している会社ですが、ある日ふと思いました。
「そういえば…私、アートフェアってちゃんと見たことないかも?」
これはいかん!ということで、勉強がてらArt Osaka 2025へ。
今回は、中之島のGalleries Sectionと北加賀屋のExpanded Section、両方をじっくり回ってきました。
(※展示期間はすでに終了しています)
結論から言うと、めちゃくちゃ良かったです。
作品の素晴らしさはもちろん、 「展示デザイン」そのものが圧倒的に学びであり、
「デザイン」というフィールドでお仕事をしている私にとっては、 ヒントと気づきの宝庫でした。
この記事では、デザイナー目線で気づいた展示設計の工夫と、印象に残った作品たちをレポート形式でお届けします。
1. 中之島:アートは“見せる”だけじゃなく、感じさせる“余白”で配置されていた
中之島のGalleries Sectionでは、いわゆる「ブース展示」のイメージとは全く異なる体験が待っていました。
正直、行く前はどんな感じなのかなとワクワクとドキドキ。「ブース展示?」「ギャラリー作品がたくさん並んでる?」。
でも実際は、全然違いました。
■ 空間設計の妙:余白が導く“感情の流れ”
まず驚いたのは、 作品間の距離感と動線の設計。
物理的な“余白”が生み出すのは、単なるスペースではなく「感情の余韻」でした。
・作品同士が干渉せず、個として立ち上がる
・鑑賞者の視線誘導がスムーズ
・通路から立ち止まる場所まで、心理的なリズムが保たれている
まさに展示は「情報配置ではなく、体験設計」だと感じました。

Galleries Section 中之島-大阪市中央公会堂
(ア)高松 威さんの作品:素材が語る有機的な力強さ
鉄板を手で曲げて形成された高松威さんの作品は、造形そのものに有機的な生命力が宿っていました。
手で曲げた後が、錆の“模様”を作り出し、作品に深みを与えていました。
そして特筆すべきは、作品の置かれ方。
上部からの柔らかい照度のもとで、影が静かに浮かび上がる。
この“静けさ”と“間”が、鑑賞者との対話を可能にしていたのです。
私には作品が“呼吸”しているように見えました。目が合ったような、一目惚れのような。
あまりに良すぎて、買っちゃいました!(ジョイ人生初、現代アート購入。)

(ア)高松威さんの作品

(イ)儀間朝龍さんの作品
(イ)儀間 朝龍さんの作品:視覚の中に潜む“記憶”を呼び起こす
儀間 朝龍さんは沖縄出身の作家で、 アメリカのポップカルチャーへの愛情と、環境への問題意識を軸に作品を制作されています。
特徴的なのは、絵の具ではなくダンボールを主素材としている点です。
最初に見たときは、リアルすぎてまさか全てがダンボールで作られているとは思いませんでした。けれど、よく見ると所々に見覚えのあるロゴや商品名が。
「これはあの配送会社の箱だ」「この切れ端、あのビールだ」と、視覚の中に潜む“記憶”を呼び起こす作品になっていたんです。
この作品が魅力的だったのは、「押しつける」のではなく、気づきを“仕込んでいる”こと。
“見せたい”という主張よりも、“違和感を設計する”ということ。
私はデザインも同じことだな、思います。
「どう見せるか」以上に、「どう感じてもらうか」「どこで気づいてもらうか」――情報ではなく“気付き”を見つけてもらうための“違和感”が大切なんだと、改めて感じました。
2. 北加賀屋:デカい、没入、心が揺れる
続いて訪れたのが、北加賀屋のExpanded Section。
こちらは“展示”というより、異世界へのインスタレーション体験でした。
造船所跡地の広大な敷地をそのまま使った空間に、どーんと作品が設置されていて、
「入った瞬間に、別の世界」**没入感**という感じ。

オノ・ヨーコさんの作品
(ウ)水田 典寿さんの作品:時間と記憶を編み直す
流木や廃材など、もともと“使われていたもの”を再構成した水田 典寿さんの作品。
表面についた傷、削れた部分、風化した色――どれもが、ただの素材ではなく、**「記憶」や「時間の蓄積」**として観る者に語りかけてきます。
特に印象的だったのは、作品と空間の“距離感”と“視点設計”。
壁際や中央にただ配置されているのではなく、建物の構造体(鉄骨や梁)との関係性を活かすようにレイアウトされていて、
まるで空間そのものが作品の一部であるかのようでした。

(ウ)水田典寿さんの作品

(エ)米津真理奈さんの作品
(エ)米津 真理奈さんの作品:壊れてなお、美しく生きる
**「壊れること」と「再生すること」**をテーマにした米津 真理奈さんの作品。
一度鋳造したガラスにあえてヒビを入れ、バラバラに砕けたものをもう一度組み直していく。その上に油彩でペイントが施されています。
まるで “壊れたものだからこそ生まれる美しさ” “傷を抱えたまま美しく生き直す” ような。静かに、でも力強く存在していました。
この作品の展示方法でとても感心したのは、鑑賞者の接近・離脱の距離設計です。
近づいてみると、細かなヒビや絵の具の筆跡に気づく。けれど、少し離れて眺めると全体のフォルムが整然として見える。
つまり、物理的な距離によって、鑑賞体験そのものが変化するように設計されていたのです。
また、自然光が差し込む時間帯に見ると、ガラスに反射する光のニュアンスが刻々と変化し、“物語が進行している”ような印象を与えてくれます。
これは単に置く場所を決めたのではなく、時間・動線・光の流れまでも計算された展示設計の成果だと感じました。
3. 展示×UX×DXって、めちゃくちゃ相性いい
ここでちょっとだけデザイナー目線の真面目な話をさせてください。
今回、展示を体験している間、何度も頭に浮かんだのは――「これってUXデザインと本質的にすごく近いな」という感覚でした。
・鑑賞者の「視線の流れ」=UI/UXにおける「導線設計」
・空間の「余白」=Webやアプリでの「ホワイトスペース」
・鑑賞後に生まれる感情の「余韻」=サービス利用後に残る「体験の記憶」
つまり、アート展示とは一種の空間におけるUX設計ではないかと感じました。
そして今、注目されている「ミュージアムDX」の文脈をそこに重ねると、さらなる可能性が見えてきます。
よくある展示のアプローチとしては、「デジタル化」「VR化」「AR体験の導入」など、“情報を増やす”方向に進みがちです。
でも今回、Art Osaka 2025を体験して思ったのは――
**むしろ「余白をつくる展示」が、これからは求められていくのでは?**ということです。
今の私たちは、常に大量の情報に囲まれて生きています。
SNS、ニュース、通知、コンテンツ…。
便利で刺激的だけれど、その分「考える前に次の情報がやってくる」構造の中にいます。
だからこそ、今回の展示のように、**情報を過剰に与えない “余白のある体験”**に、今は価値があると感じます。
つまり、
** “情報を増やすDX”より、“余白をつくるDX” が今後求められていくのではないか**ということです。

Expanded Section 北加賀屋-クリエイティブセンター大阪

李吉來さんの作品

金春載さんの作品
おわりに|“人の心に残る体験”を生み出す
アートフェアって、これまで“知識を得る場”だと思っていました。
でも実際に訪れて感じたことは、
「体験する」ことで、鑑賞者の中に感情が芽生えるということ。
そして、今度は私自身が**“届ける側”としてこの体験を設計してみたい**と思いました。
以上、デザイナー目線でお届けした Art Osaka 2025 ジョイのレポートでした。
読んでくださり、ありがとうございました!
※本記事は、Art Osaka事務局様のご厚意により掲載許可をいただいております。また、展示や写真の著作権は主催者に帰属し、権利を尊重した形で魅力が正しく伝わるよう心がけてご紹介しております。